
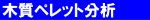
2016.11.15日本ペレット協会の規格が改定されました。新規格について、改訂に関する部分は赤字で、古い記述は消し線で残しました。
 20161115改定 20161115改定
 長さに関する改訂のご説明 長さに関する改訂のご説明
 従来は「木質ペレット品質規格原案 H19.9.21作成」を元に測定することが多かったのですが、平成23年3月に「木質ぺレット品質規格」が一般社団法人 日本木質ペレット協会から出されました。 従来は「木質ペレット品質規格原案 H19.9.21作成」を元に測定することが多かったのですが、平成23年3月に「木質ぺレット品質規格」が一般社団法人 日本木質ペレット協会から出されました。
 日本木質ペレット協会 日本木質ペレット協会
「木質ペレット品質規格」のほかに下記のような資料、規格も参考にして総合的に評価する場合もあります。
・ペレットクラブによる規格
「木質ペレット燃料に関するペレットクラブ自主規格」
PC WPFS‐1:2011 2011年6月6日 改定
 ペレットクラブ ペレットクラブ
・木質ペレット品質規格原案 H19.9.21作成
財団法人 日本住宅・木材技術センター
・廃棄物固形燃料試験方法 JIS Z 7302
・岩手県木質ペレット規格案策定事業
各種資料 など
「木質ペレット品質規格」(以下、”新規格”)に定められた主な分析・測定項目(品質管理項目)には以下のようなものがあります。
 木質ぺレット品質規格 木質ぺレット品質規格
 20161115改定 20161115改定
 長さの改訂に関するご説明 長さの改訂に関するご説明
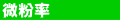 (びふん (びふんりつ)
改訂で”微粉”と呼ぶことになりました。
微粉(3.15mmのふるいから落ちたもの)が含まれる割合を微粉率と言います。微粉率は新規格から必須項目になっています。改定によって”微粉率”は”微粉”と呼ぶことになりました。在庫時の状況、運搬状況、取扱い方等によっても変わってしまうので注意が必要です。
原案では2.8mmのふるいでしたが新規格では”3.15mm丸穴板ふるい”を使用することのなりました。
 
3.15mm
丸穴
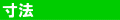
直径(太さ)、長さが測定対象になります。
直径はノギスなどで50粒、計測して求めます。成型機の規格により6〜12mm程度のものまでありますが、新規格では呼び径で6mmと8mmを標準としています。当面は7mmのものも認めるとされています。 改訂で7mmのものは規定外となりました。
 長さは約250gを3組、調査します。その中に長さ 長さは約250gを3組、調査します。その中に長さ30mm40mmを超えるものがどのくらいの割合で含まれているか求めます。95%以上1%未満が基準になります。また、”長さ40mm45mmを超えるものが無い”こととされました。規定を超えて長いものは自動供給機に支障がある場合があるとされています。
 20161115改定 20161115改定
 長さの改訂に関するご説明 長さの改訂に関するご説明
 木質ペレットは、間伐材や木材の加工時に発生するおがくず、樹皮などを高圧で押し固めて成型する。成型機により太さ6〜12mmのものが生産されている。成型は木材成分のリグニンが熱によって融解し固めることができるため接着剤などの化学製品や添加物を一切使用していないため安心。(一部では、建築廃材や流木などを加工したものも木質ペレットと称している場合がある) チップなどより単位体積当たりの発熱量が高く、大きさや形状の規格が均一であるため取り扱いが容易。 木質ペレットは、間伐材や木材の加工時に発生するおがくず、樹皮などを高圧で押し固めて成型する。成型機により太さ6〜12mmのものが生産されている。成型は木材成分のリグニンが熱によって融解し固めることができるため接着剤などの化学製品や添加物を一切使用していないため安心。(一部では、建築廃材や流木などを加工したものも木質ペレットと称している場合がある) チップなどより単位体積当たりの発熱量が高く、大きさや形状の規格が均一であるため取り扱いが容易。 大気中の二酸化炭素の総量を増加させないカーボンニュートラルなエネルギーとしてストーブやボイラーなどの燃料としても注目されている。また、輸入に頼らない国産エネルギーとしても価値がある。 大気中の二酸化炭素の総量を増加させないカーボンニュートラルなエネルギーとしてストーブやボイラーなどの燃料としても注目されている。また、輸入に頼らない国産エネルギーとしても価値がある。 |
 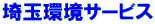 では では
木質ペレット以外にも、木質チップ、固形燃料(RDF,RPF)、高分子廃棄物等の発熱量測定、灰分測定等が可能です。高位発熱量、低位発熱量の算出、元素分析も可能。お気軽にご連絡ください。 |
  |

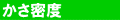
単容積当たりの重さを測定する。何度か測定して平均値を求めます。原案では簡易測定法も規定されていましたが、新規格では簡易測定法はありません。
新規格では650kg/m3以上、750kg/m3以下と定められています。直感的には判りにくいかも知れませんが
”650kg/m3” とは、
"1リットル当たりの重さが650g"と同義になります。
1リットルの水は約1000gとなります。
 (きかいてきたいきゅうせい) (きかいてきたいきゅうせい)
原案には無かった項目ですが、意味合い的には原案の粉化度と似ています。耐久性試験機に入れ、規定の回転を加えた後にふるい、微粉の割合を調べます。原案の粉化度の試験では袋に入れて規定の高さから落とすなどの作業で求められましたが、機械的耐久性は耐久性試験機が無いと測定できなくなりました。測定方法が違う為、粉化度と数値を比較することはできません。換算する事もできません。容易に粉にならない方が品質が良いことになります。
新規格では97.5%以上と定められています。微粉になってしまうのが2.5%未満と言う事です。
改訂で区分分けされました
 20161115改定 20161115改定
 機械的耐久性試験機紹介 機械的耐久性試験機紹介
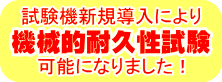
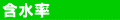 (がんすいりつ) (がんすいりつ)
改訂で湿量基準含水率M 水分(湿量基準含水率)と呼ぶことになりました。
 20161115改定 20161115改定
105℃で乾燥させ、乾燥前の重量と乾燥後の重量から水分の割合を求める。この規格では湿重量基準だが、他の試験では乾重量基準の場合もあるため注意が必要です。
水分は熱量を下げてしまったり、カビの発生の原因にもなるため一定以下に管理されていることが望まれる。
新規格では10%以下と定められています。
 (はつねつりょう) (はつねつりょう)
燃やしたときにどれだけの発熱量を持っているかの測定です。条件(ベース)によって、数値が異なる。品質規格では有姿(そのままの状態)での発熱量となっているが、高位発熱量や、低位発熱量を求めたりする。低位発熱量は水分と実測発熱量の測定と水素の含有量が必要になります。
新規格では水素の含有量を一律に6%としてよいとしています。新規格では高位発熱量、低位発熱量が品質区分ごとに定められ、さらにJ(ジュール)とcal(カロリー)が併記されています。
改訂ではカロリーの表記はなくなりました
 20161115改定 20161115改定
 ごみ質分析 発熱量 ごみ質分析 発熱量
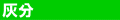 (かいぶん) (かいぶん)
815℃でペレットを燃やして、残った灰の割合を求める。木の部分によって、また樹種によっても違いがあるが、少ないことが望ましい。灰分が少ないと、燃やした後の灰の発生量が少ないことを意味する。
規格では灰分の値によってA、B、Cの3区分の品質基準に分かれます。Aがより品質が高い(良い)と言えます。この区分によって、発熱量、硫黄分、塩素、機械的耐久性、窒素の基準値が違います。
A : 0.5%以下
B : 0.5%超、1.0%以下
C : 1.0%超、5.0%以下 2.0%以下(改訂)
 20161115改定 20161115改定
 木質ぺレット品質規格 木質ぺレット品質規格

塩素、硫黄などは燃やしたときに有害な酸性ガスを発生したり、ダイオキシンなどの発生原因になることがあります。少ないことが望ましい。塩素と硫黄と窒素の基準値は灰分の値によって定められる、品質区分に応じて品質基準が違います。
硫黄、窒素、塩素に基準が設けられました。
 20161115改定 20161115改定
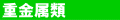
重金属類は有害なことも多く、少ないことが望ましい。燃やしたときに気化して飛散するものや、灰の中に残留するものがあります。
天然由来(もともと含まれるもの)のものもあるが、人工的に処理(防腐剤、防カビ剤、防シロアリ剤、塗料など)することで含まれることがあります。そうしたことの目安にもなります。原料を厳選、管理することが大切です。
ヒ素、カドミウム、全クロム、銅、水銀、ニッケル、鉛、亜鉛に基準が設けられました。
規定にはありませんがその他の項目として
・灰の物性(融点など)
・放射能(セシウムなど)
を測定することもあります。
|