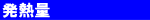

 偛傒丄攑婞暔偺張棟曽朄偼偄傠偄傠偁傝傑偡偑丄傑偩憡摉偺検偑從媝偝傟偰偄傑偡丅偦偺偨傔擱傗偟偨偲偒偵丄偳偺偔傜偄偺敪擬検偑偁傞偺偐抦傞昁梫偑弌偰偒傑偡丅從媝楩傪愝寁偡傞忋偱傕丄擱從忬懺傪娗棟偡傞忋偱傕丄偛傒偺惈忬傪攃埇丄僄僱儖僊乕廂巟偺攃埇側偳偱傕戝愗側巜昗偵側傝傑偡丅嵟嬤偱偼丄偛傒偺僄僱儖僊乕偱敪揹偟丄峏偵偼攧揹偡傞堊偵昁梫惈偼憹偟偰偄傑偡丅 偛傒丄攑婞暔偺張棟曽朄偼偄傠偄傠偁傝傑偡偑丄傑偩憡摉偺検偑從媝偝傟偰偄傑偡丅偦偺偨傔擱傗偟偨偲偒偵丄偳偺偔傜偄偺敪擬検偑偁傞偺偐抦傞昁梫偑弌偰偒傑偡丅從媝楩傪愝寁偡傞忋偱傕丄擱從忬懺傪娗棟偡傞忋偱傕丄偛傒偺惈忬傪攃埇丄僄僱儖僊乕廂巟偺攃埇側偳偱傕戝愗側巜昗偵側傝傑偡丅嵟嬤偱偼丄偛傒偺僄僱儖僊乕偱敪揹偟丄峏偵偼攧揹偡傞堊偵昁梫惈偼憹偟偰偄傑偡丅
丂敪擬検偑掅偡偓傞偲丄擱椏傪壛偊側偄偲姰慡偵擱傗偡偙偲偑偱偒側偐偭偨傝丄崅偡偓傞偲楩偵晧扴傪妡偗偰偟傑偄丄楩偺庻柦傪弅傔偰偟傑偆偙偲偵側偭偨傝偟傑偡丅
 偛傒偺惈忬偼捠忢丄怲廳偵僒儞僾儕儞僌偟偰傕偐側傝偺僶儔僣僉傪娷傫偱偄傑偡丅傑偨丄揤岓丄婫愡丒帪婜側偳偵傛偭偰傕曄摦偟傑偡偟丄偳傫側偵拲堄偟偰傕嬼慠偵傛傞曃傝摍傪攔彍偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅曅婑傝偑側偄傛偆偵怱妡偗偰僒儞僾儕儞僌偡傞偙偲偼摉慠丄廳梫偱偡偑丄應掕夞悢傪廳偹丄僶儔僣僉孹岦傗丄戝偒側曄摦孹岦偵拲栚偡傞偙偲傕戝愗偱偡丅 偛傒偺惈忬偼捠忢丄怲廳偵僒儞僾儕儞僌偟偰傕偐側傝偺僶儔僣僉傪娷傫偱偄傑偡丅傑偨丄揤岓丄婫愡丒帪婜側偳偵傛偭偰傕曄摦偟傑偡偟丄偳傫側偵拲堄偟偰傕嬼慠偵傛傞曃傝摍傪攔彍偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅曅婑傝偑側偄傛偆偵怱妡偗偰僒儞僾儕儞僌偡傞偙偲偼摉慠丄廳梫偱偡偑丄應掕夞悢傪廳偹丄僶儔僣僉孹岦傗丄戝偒側曄摦孹岦偵拲栚偡傞偙偲傕戝愗偱偡丅
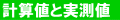
 敪擬検偺抣偼悈暘丄奃暘側偳偺抣偐傜寁嶼偱媮傔傞寁嶼抣乮悇嶼抣乯偲丄幚嵺偵偛傒偺僒儞僾儖偺敪擬検傪應掕偡傞幚應抣偑偁傝傑偡丅椉曽傪媮傔傞応崌傕偁傝傑偡丅
敪擬検偺抣偼悈暘丄奃暘側偳偺抣偐傜寁嶼偱媮傔傞寁嶼抣乮悇嶼抣乯偲丄幚嵺偵偛傒偺僒儞僾儖偺敪擬検傪應掕偡傞幚應抣偑偁傝傑偡丅椉曽傪媮傔傞応崌傕偁傝傑偡丅

 寁嶼抣偼悈暘偲壜擱暘偺抣偐傜媮傔傞傕偺乮娐惍俋俆崋偺俁惉暘偺幃乯偐傜丄尦慺慻惉妱崌偵傛傞傕丄暔棟慻惉斾偵傛傞傕偺側偳丄偄傠偄傠側寁嶼幃乮悇嶼幃乯偑偁傝傑偡丅
寁嶼抣偼悈暘偲壜擱暘偺抣偐傜媮傔傞傕偺乮娐惍俋俆崋偺俁惉暘偺幃乯偐傜丄尦慺慻惉妱崌偵傛傞傕丄暔棟慻惉斾偵傛傞傕偺側偳丄偄傠偄傠側寁嶼幃乮悇嶼幃乯偑偁傝傑偡丅
丂扨偵"寁嶼抣"偲尵偆偲乭娐惍俋俆崋偺嶰惉暘偺幃乭偑堦斒揑偱偡丅偑丄偍媞條偵傛偭偰偼撈帺偺寁嶼幃傪梡偄傞応崌傕偁傝傑偡偺偱妋擣偑昁梫偱偡丅

丒斾妑揑庤寉偵掅埵敪擬検傪媮傔傞偙偲偑偱偒傞丅堦斒偵嶼弌偵昁梫側崁栚偑彮側偄堊丄僐僗僩傪梷偊傞偙偲偑偱偒傞丅乮娐惍俋俆崋偺幃偱偼悈暘偲壜擱暘偐傜嶼弌偱偒傞乯

丒慖戰偡傞悇嶼幃偵傛偭偰偼僐僗僩偑埨偄偲偼尷傜側偄丅乮尦慺慻惉偑昁梫偩偭偨傝乯
丒偁偔傑偱傕寁嶼偵傛傝敪擬検傪悇嶼偡傞傕偺偱丄偛傒偺惈忬偵傛偭偰偼幚嵺偺敪擬検偲戝偒偔堎側傞応崌傕偁傞丅
丒偨偲偊偽娐惍俋俆崋偺寁嶼幃偺応崌丄壜擱暘偺敪擬検傪堦棩偵憐掕偟偰偄傞偨傔丄偛傒偺慻惉偵傛偭偰偼幚嵺偲戝偒偔堎側傞偙偲偑懡偄丅摿偵崅暘巕宯乮僾儔丄價僯乕儖乯偺妱崌偑懡偄専懱偱偼丄懡偔偺応崌丄寁嶼抣傛傝幚應抣偺傎偆偑偐側傝崅偄丅
 丂乮娐惍俋俆崋偵偼婯掕偝傟偰偄側偄乯 丂乮娐惍俋俆崋偵偼婯掕偝傟偰偄側偄乯
 幚應抣偼僒儞僾儕儞僌偟偨偛傒乮専懱乯傪姡憞偝偣丄慻惉偛偲偵暘偗偨傕偺乮壜擱暔偺傒乯傪屄乆偵暡嵱偟丄尦偺慻惉妱崌偱崿崌偟偨帋椏偺敪擬検傪幚嵺偵應掕偟丄悈暘丄悈慺検乮悈慺偺應掕偑昁梫偱偡乯側偳偱媮傔傑偡丅 幚應抣偼僒儞僾儕儞僌偟偨偛傒乮専懱乯傪姡憞偝偣丄慻惉偛偲偵暘偗偨傕偺乮壜擱暔偺傒乯傪屄乆偵暡嵱偟丄尦偺慻惉妱崌偱崿崌偟偨帋椏偺敪擬検傪幚嵺偵應掕偟丄悈暘丄悈慺検乮悈慺偺應掕偑昁梫偱偡乯側偳偱媮傔傑偡丅

丒幚嵺偺偛傒偺慻惉忬嫷丄惈忬傪斀塮偟偨幚嵺偵嬤偄抣傪媮傔傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丒應掕崁栚偑懡偔側傝僐僗僩偑崅偔側傞偙偲傕偁傞丅乮慻惉斾棪丄敪擬検偺幚應丄悈慺偺應掕偑昁恵偲側傝傑偡乯
丂 敪擬検悇嶼抣丂 敪擬検悇嶼抣丂
丂丂戙昞揑側悇嶼幃傪徯夘偟傑偟偨丅
丂 娐惍俋俆崋敳悎媦傃丄夝愢 娐惍俋俆崋敳悎媦傃丄夝愢
丂 偛傒幙暘愅偺棳傟 偛傒幙暘愅偺棳傟
丂 嶲峫恾彂偺徯夘 嶲峫恾彂偺徯夘
丂丂偛傒暘愅偺嶲峫偵側傞恾彂偺徯夘丅
丂 栘幙儁儗僢僩暘愅丄應掕 栘幙儁儗僢僩暘愅丄應掕
丂  
|

 敪擬偺梡岅偵偮偄偰偼堦晹丄崿棎偟偰梡偄傜傟傞応崌傕偨傑偵尒庴偗傜傟傑偡丅傑偨丄挷惢偝傟偨僒儞僾儖儀乕僗側偺偐丄尦偺惗偛傒偵偮偄偰側偺偐偵傛偭偰傕丄昞尰偑堘偭偰偒傑偡丅埲壓偵偮偄偰傕偦偺揰傪峫椂偺忋丄偛棗壓偝偄丅偦傟偧傟偺応崌偵偮偄偰丄偳偺悢抣偑昁梫側偺偐丄媮傔傜傟偰偄傞傕偺偼壗偐妋擣偡傞昁梫傕偁傝傑偡丅偼偭偒傝尵偭偰敾傝偯傜偄偟丄愢柧偑峴偒撏偐側偄晹暘傕偁傞偲巚偄傑偡丅偛傔傫側偝偄丅
敪擬偺梡岅偵偮偄偰偼堦晹丄崿棎偟偰梡偄傜傟傞応崌傕偨傑偵尒庴偗傜傟傑偡丅傑偨丄挷惢偝傟偨僒儞僾儖儀乕僗側偺偐丄尦偺惗偛傒偵偮偄偰側偺偐偵傛偭偰傕丄昞尰偑堘偭偰偒傑偡丅埲壓偵偮偄偰傕偦偺揰傪峫椂偺忋丄偛棗壓偝偄丅偦傟偧傟偺応崌偵偮偄偰丄偳偺悢抣偑昁梫側偺偐丄媮傔傜傟偰偄傞傕偺偼壗偐妋擣偡傞昁梫傕偁傝傑偡丅偼偭偒傝尵偭偰敾傝偯傜偄偟丄愢柧偑峴偒撏偐側偄晹暘傕偁傞偲巚偄傑偡丅偛傔傫側偝偄丅
丂擖壸儀乕僗丄桳巔儀乕僗丄晽姡儀乕僗丄愨姡儀乕僗側偳偺昞尰傕巊傢傟傑偡偑丄憃曽偺擣幆傪妋擣偟側偄偲娫堘偊偺尨場偵側傝傑偡丅傎偐偵傕惗偛傒儀乕僗乮幖儀乕僗乯丄姡憞偛傒儀乕僗丄姡憞壜擱暔儀乕僗丂側偳側偳
亂幚應偵傛傞掅埵敪擬検應掕亃
丂偛傒幙暘愅偺応崌丄堦斒揑偵偼嵟廔揑偵偼掅埵敪擬検偑抦傝偨偄乮偙偲偑懡偄乯丅丂偦偺偨傔偵偼丄
嘆姡憞偝偣傞乮悈暘偺彍嫀乯
嘇慻惉偛偲偵暘偗偰妱崌傪媮傔傞丅
丂丂丂晄擱暔偺妱崌傪媮傔傞丅
嘊壜擱暔偺傒傪暡嵱偟偰尦偺妱崌偱崿崌偟丄敪擬検應掕梡丄悈慺應掕梡偺帋椏偲偟傑偡丅
偙偺傛偆偵挷惢偟偨僒儞僾儖傪乭壔妛暘愅帋椏乭偲屇傇偙偲傕偁傝傑偡丅
嘋寁嶼偵傛偭偰丄姡憞慜偺惗偛傒忬懺偺抣偵姺嶼偟傑偡丅乮悈暘丄晄擱暔傪妱傝栠偡乯
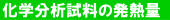 丂Hh-B 丂Hh-B
丒幚嵺偵敪擬検寁偵搳擖偡傞忬懺偵挷惢偟偨帋椏偺敪擬検丅
丒傕偲偺専懱乮惗偛傒摍乯偐傜悈暘偲晄擱暔傪彍偄偨丄姡憞忬懺偺壜擱暔傪尦偺妱崌偱崿崌偟偨傕偺丅抐擬忬懺偱應掕偟偨敪擬検丅
丒偙傟傪憤敪擬検偲尵偆偙偲傕偁傞丄偲尵偆偐摨偠抣偵偵側傞偙偲偑偁傞丅乮悈暘侽亾丄晄擱暔侽亾丄偁傞偄偼偦傟傪娷傔偰偺専懱偲偟偨応崌乯 (仼偡偄傑偣傫丅敾傝偢傜偄偱偡傛偹乯
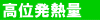 丂Hh 偁傞偄偼 Ho 丂Hh 偁傞偄偼 Ho
丒崅敪擬検偲傕尵偆丅憤敪擬検偲傕尵偆丅専懱偑偛傒慡懱偲偡傞応崌偼捠忢偼姡憞丄晄擱暔彍嫀偝傟傞偨傔悈暘媦傃晄擱暔妱崌偱曗惓偟偛傒慡懱偵姺嶼偡傞丅
(仼偡偄傑偣傫丅敾傝偢傜偄偱偡傛偹乯
丒悈暘偑擬傪扗偆慜偺擬検丄偁傞偄偼扗偭偨偲偟偰傕奜晹偵曻弌偝傟偢栠偭偰偔傞忬懺偱偺敪擬検丅
丒愨姡乮柍悈乯儀乕僗偺崅埵敪擬検偺応崌偼晄擱暔曗惓偺傒偱悈暘曗惓偼晄梫乮侽偲側傞乯偲側傝傑偡丅晄擱暔偑側偐偭偨応崌偵偼壔妛暘愅帋椏偺敪擬検偲堦抳偟傑偡丅
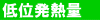 丂Hl 偁傞偄偼 Hu 丂Hl 偁傞偄偼 Hu
丒掅敪擬検丄恀敪擬検偲傕尵偆丅
丒崅埵敪擬検偐傜悈暘偑扗偆擬検乮忲敪愽擬乯丄偍傛傃悈慺偑悈偵側偭偰扗偆擬検傪嵎偟堷偄偨抣丅
丒幚嵺偵棙梡偱偒傞暘偺擬検丅
丒堦斒揑偵偼偙傟偑抦傝偨偄偙偲偑懡偄丅
丒悈暘偺娷桳検偱戝偒偔曄摦偟傑偡丅
丒愨姡乮柍悈乯儀乕僗偺掅埵敪擬検偺応崌偼悈暘偑扗偆擬検乮忲敪愽擬乯偼柍偄傕偺偲偟悈慺偑悈偵側偭偰扗偆擬検偺傒傪嵎偟堷偒傑偡丅偦偺嵺偺悈慺亾傕愨姡乮柍悈乯儀乕僗偲偟儀乕僗傪崌傢偣傞昁梫偑偁傝傑偡丅
丒尦偺敪擬検偑彫偝偐偭偨傝乮濨枂側昞尰偱偡傒傑偣傫乯丄悈暘偑懡偄偲嶼弌偟偨掅埵敪擬検偑儅僀僫僗偵側傞偙偲傕偁傝傑偡丅
乮儅僀僫僗偺敪擬検偭偰偳偆尵偆帠偩偲丄偛幙栤傪捀偔偙偲傕偁傝傑偡偑乯
丂寢峔丄傔傫偳偔偝偄榖偩偲巚偆偺偱偛憡択偔偩偝偄丅
 僇儘儕乕(cal)偲僕儏乕儖(J) 僇儘儕乕(cal)偲僕儏乕儖(J)
丂寁検朄偱偼丂侾俰亖係丏侾俉係cal丂偲掕媊偝傟偰偄傑偡丅4.18605偲偝傟偰偄偨帪戙傕偁傞偨傔丄偙偺抣偑巆偭偰偄傞帒椏丄暥專傕懡偄丅偦偺懠偵傕偄傠偄傠側掕媊傗悢抣偑偁傞偑丄寁検朄偱偼
丂侾cal亖係丏侾俉係J丂
偲掕媊偝傟偰偄傑偡丅
丂側偺偱丂侾俰亖栺0.2390們倎倢丂偲側傞丅乭栺乭偱偡丅抂悢偑弌傞偨傔偱偡丅JIS偱偼傑偨暿偵掕媊偝傟偰偄傞応崌傕偁傝傑偡丅 |

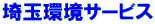 偱偼 偱偼
偛傒幙偺傎偐丄墭揇丄屌宍擱椏丄儁儗僢僩丄崅暘巕攑婞暔摍偺敪擬検應掕偑壜擻偱偡丅崅埵敪擬検丄掅埵敪擬検偺嶼弌丄尦慺暘愅傕壜擻丅丂偍婥寉偵偛楢棈偔偩偝偄丅 |
|