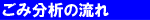 (標準の場合) (標準の場合)


乾燥(水分測定)
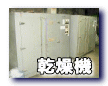 乾燥機で乾燥させ、乾燥の前後の重量から水分を求める。 乾燥機で乾燥させ、乾燥の前後の重量から水分を求める。
熱風循環式大型乾燥機。 |


破砕、粉砕
 組成分析したものの可燃物を項目ごとに破砕し粉状にする。 組成分析したものの可燃物を項目ごとに破砕し粉状にする。 |

調製 (乾燥可燃物を破砕した試料をを組成の比率で混合する)
”化学分析試料”と呼んだりする
|
  
破砕機、粉砕機の紹介(弊社のもの)
 上部から試料を入れると、高速で回転する6枚の回転刃と、2枚の固定刃によって切断、粉砕され一定以下の粒径になった物が下部のメッシュを通過して受け皿に落ちるようになっている。 ウィレー式とか言う型式らしい。刃を研磨したり、隙間を調整したりと、なかなか職人領域の機械かもしれない。 上部から試料を入れると、高速で回転する6枚の回転刃と、2枚の固定刃によって切断、粉砕され一定以下の粒径になった物が下部のメッシュを通過して受け皿に落ちるようになっている。 ウィレー式とか言う型式らしい。刃を研磨したり、隙間を調整したりと、なかなか職人領域の機械かもしれない。 |
元素分析機の紹介(弊社のもの)
 上部から試料が投入されると、酸素中で完全燃焼され、炭素分はCO2に、水素はH20に、窒素はN2Oになりヘリウムのキャリアで運ばれTCD検出器と赤外線検出器で測定する。LECO社製。(写真はパーキンエルマー社の時のもの) 上部から試料が投入されると、酸素中で完全燃焼され、炭素分はCO2に、水素はH20に、窒素はN2Oになりヘリウムのキャリアで運ばれTCD検出器と赤外線検出器で測定する。LECO社製。(写真はパーキンエルマー社の時のもの) |
大型乾燥機の紹介(弊社のもの)
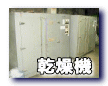 大人が広げた手の幅くらいある電気式乾燥機。熱風循環式乾燥機とよばれ中にファンがあり内部で熱風を循環させている。弊社のものは中に8段のパレットがある。通常の10kg程度の一般可燃ごみだと3〜7日程度で乾燥が完了する。”105℃で”とする資料も多いがこの温度では発火、発煙、変質してしまうので、それより低い温度で乾燥させることが多い。 大人が広げた手の幅くらいある電気式乾燥機。熱風循環式乾燥機とよばれ中にファンがあり内部で熱風を循環させている。弊社のものは中に8段のパレットがある。通常の10kg程度の一般可燃ごみだと3〜7日程度で乾燥が完了する。”105℃で”とする資料も多いがこの温度では発火、発煙、変質してしまうので、それより低い温度で乾燥させることが多い。 |
  
 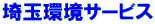 では では
ごみ質分析全般が可能です。サンプリングから、乾燥、破砕・粉砕、組成分析(仕分け、分別)、灰分測定、発熱量測定、元素分析等。 お気軽にご連絡ください。 |
|
 ごみ分析の基本的な流れは環整95号に記載されています。 ごみ分析の基本的な流れは環整95号に記載されています。
 環整95号抜粋及び、解説 環整95号抜粋及び、解説
お客様の仕様によって順番が変わったり、項目が加除されることもあります。
 サンプリング、検体の採取 サンプリング、検体の採取
ゴミピットからクレーンで上げてもらったものから、縮分したり、パッカー車から採取したりする。縮分は円錐四分法による。何の分析でもそうでしょうが、このサンプリングの良し悪しで決まると言っても過言ではない。
 円すい四分法 円すい四分法
 単位容積重量(見掛け比重)測定 単位容積重量(見掛け比重)測定
時間の経過や運搬中に容量が変わるので容量の確認は採取の現場でやることが望ましい。
容量が既知の容器にごみを入れ、容量あたりの重量を測る。一般には30〜50リットル程度のバケツや箱を利用する。30センチ程度のところから3回トントンと落とすので割れたり壊れたりするものでは困る。
仕様によっては一定量の荷重を加えた時の容量を測るように指示されることもある。
 乾燥(水分測定) 乾燥(水分測定)
乾燥機で乾燥させ、乾燥の前後の重量から水分を求める。
 物理組成(仕分け、分別) 物理組成(仕分け、分別)
環整95号では乾燥後に分別することになっているが、湿状態で仕分けすることもある。
そうすることにより組成項目個々の水分(含水率)を知ることができる。
 物理組成分析(分別) 物理組成分析(分別)
 破砕、粉砕 破砕、粉砕
可燃物を組成ごとに1〜2mm以下に破砕し粉状にする。イメージとしてはふりかけ程度(あるいはもう少し細かく)の粒径。
 調製(”調整”ではありません) 調製(”調整”ではありません)
1〜2mm以下に破砕し粉状になった組成項目ごとの試料を元の組成割合に応じて混合する。それが元の試料を代表する検体となる。
通常は乾燥状態の可燃物のみを混合するため、有姿(入荷状態、湿状態)の値を求めるためには水分と破砕・混合を除外した分(通常、不燃物など)の補正・換算をする必要がある。
 各種分析 各種分析
 発熱量(低位、高位発熱量) 発熱量(低位、高位発熱量)
発熱量実測(ボンブ式)
 ごみの3成分 ごみの3成分
水分、灰分、可燃分
 灰分測定 灰分測定
灰分(かいぶん)測定の紹介
 粉砕した可燃物をるつぼに入れ800℃で強熱する。残った灰の割合から求める。ここでは各可燃物の灰分が測定できるが、三成分(全体の)灰分は組成割合、不燃物割合なども含め計算で求める。 粉砕した可燃物をるつぼに入れ800℃で強熱する。残った灰の割合から求める。ここでは各可燃物の灰分が測定できるが、三成分(全体の)灰分は組成割合、不燃物割合なども含め計算で求める。
 灰分測定 灰分測定
 ごみの3成分 ごみの3成分 |
その他に元素組成分析など
(炭素、水素、窒素、
硫黄、塩素、酸素など)
|