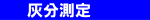 (カイブン測定) (カイブン測定)

環整95号では、灰分測定について以下のように記載されています。ごみ質分析の中でも判りにくい部分だと思いますにで説明します。
この灰分と、水分、可燃分を”ごみの三成分”といい、ごみの基本的な指標の一つです。
---環整95号から灰分測定部分のみ抜粋---
 分別した六組成のうち、不燃物類を除き、 分別した六組成のうち、不燃物類を除き、
 各組成ごとに破砕機を用いて 各組成ごとに破砕機を用いて
2mm以下に粉砕し、
 その一部をルツボに入れて その一部をルツボに入れて
105℃±5℃で2時間加熱する。
これを秤量したのち、
 電気炉を用いて800℃で2時間強熱し、 電気炉を用いて800℃で2時間強熱し、
秤量する。
 灰分は、次式(3)、(4)および(5)により算出する。 灰分は、次式(3)、(4)および(5)により算出する。
 各組成の灰分(%)=(強熱後の重量〔kg〕 各組成の灰分(%)=(強熱後の重量〔kg〕
/強熱前の重量〔kg〕)×100 …(3)
 乾燥ごみの灰分(%)= 乾燥ごみの灰分(%)=
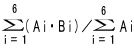 …(4) …(4)
Ai:(3)で求めた各組成iの重量比(%)
Bi:各組成iの灰分(%)
(不燃物類については100とする。)
 生ごみの灰分(%)=乾燥ごみの灰分(%) 生ごみの灰分(%)=乾燥ごみの灰分(%)
×((100−水分(%))/100) …(5)
|
 環整95号抜粋及び、解説 環整95号抜粋及び、解説
 ごみ質分析の流れ ごみ質分析の流れ
 ごみの3成分 ごみの3成分
 参考図書の紹介 参考図書の紹介
ごみ分析の参考になる図書の紹介。
  

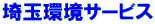 では では
灰分測定をはじめ、ごみ質分析全般が可能です。 お気軽にご連絡ください。 |
|

この記載だけではなかなか判りづらいと思います。
環整95号から灰分測定部分のみ抜粋し、工程ごとに区切って説明します。
 分別した6組成のうち、5の不燃物類を除いた以下の5項目が対象になります。 分別した6組成のうち、5の不燃物類を除いた以下の5項目が対象になります。
1 紙・布類
2 ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類
3 木・竹・ワラ類
4 ちゆう芥類
6 その他
 対象の5項目についてそれぞれ破砕機を用いて2mm以下に粉砕する。 対象の5項目についてそれぞれ破砕機を用いて2mm以下に粉砕する。
 粉砕した5項目についてそれぞれその一部をルツボに入れて105℃±5℃で2時間加熱し完全に乾燥させます。水分が残っていたり、後から水分を吸ってしまったりした分を完全に0にする。 粉砕した5項目についてそれぞれその一部をルツボに入れて105℃±5℃で2時間加熱し完全に乾燥させます。水分が残っていたり、後から水分を吸ってしまったりした分を完全に0にする。
 乾燥後、放冷し”強熱前の重量”を秤量する。 乾燥後、放冷し”強熱前の重量”を秤量する。
 電気炉を用いて800℃で2時間強熱し、放冷後、”強熱後の重量”を秤量する 電気炉を用いて800℃で2時間強熱し、放冷後、”強熱後の重量”を秤量する
 各組成の灰分は式(3)から求める。 各組成の灰分は式(3)から求める。
 おそらく、この式(4)が難解かと・・。 おそらく、この式(4)が難解かと・・。
分母(右半分):組成重量比の合計
不燃物まで含めた6項目合計は100になる。
分子(左半分):こちらが重要。本質の部分。
各組成ごとに 重量比×灰分 を求め。
6項目分足したもの。その際、不燃物は燃やしてみていないが(燃やさない。燃やせない)、灰分100%として計算するする。
意味的には”乾燥ごみ全体を燃やしたとしたら何%が灰として残るか”と言うこと。
 求めた灰分は”乾燥ごみの灰分”であるため、水分で補正して生ごみベース(湿ベース、採取ベース)に換算する。 求めた灰分は”乾燥ごみの灰分”であるため、水分で補正して生ごみベース(湿ベース、採取ベース)に換算する。
 式4が理解しにくいときは、比率ベースでなく、重量ベースで考えると直感的で判り易いかもしれません。 式4が理解しにくいときは、比率ベースでなく、重量ベースで考えると直感的で判り易いかもしれません。
分母(右半分):
乾燥後重量(各組成重量の合計)
分子(左半分):
各組成ごとに 重量×灰分 を求め。
6項目分足す。
こう置き換えて求めた分子の値は乾燥ごみを全量燃やしたと仮定したときの灰(燃え残り)の重量。 そう考えると生ごみ換算も簡単に理解できるかと思います。
|