●安全について1
【乾燥、強熱、破砕編】
以下はごみを分析する同志が事故に合わないよう参考に書いてみました。これが必ずしも正しいとは限りませんし。この通りにやって被害が増大しても責任も取れません。が、ほんの少しでも参考になれば幸いです。事態を想定して対策して置くことも大切です。そして何より、そうならないように予防する事が大切です。
【熱風循環式の乾燥機の安全について。特に火災防止について】
・環整95号では105℃±5℃で乾燥するようになっていますが、この温度ではかなりの確率で出火します。やってみれば分かりますが危険です。やってみない方がいいです。
低めに温度を管理しても部分的に温度が高い場所がある可能性もあり、安心できません。
・なので実際にはもっと低い温度で時間を掛けて乾燥させます。
・別のページにも禁忌品として例を挙げてありますがこれらが入っている場合、出火、爆発の確率が高まります。サンプリング工程、乾燥機に入れる工程、写真を撮る際でも気がついたら必ず取り除いてください。
【禁忌品】乾燥機に入れない
カセットコンロのボンベ、スプレー缶、ライター、マッチ、花火(燃えカスも)、有機溶剤(接着剤、ペンキ、マニキア、香水なども)などは乾燥機に入れない。
その他にも油の浸みたキッチンペーパー、ティッシュ、布、綿状のもの、カンナの削りカス状のもの、天かすなどは要注意です。最近では消毒用のアルコールが付着した紙や布などにも注意する必要があります。
【発火、出火した場合】
・排気口から煙が出ている。
・設定温度より大幅に高くなっている。
・温度アラームが鳴っている。
・異臭で気付く場合もあります
などの場合は内部で発火した可能性があります。
絶対に慌てて扉を開けないこと!
・できる状況(ドアが熱くなっていたりすると危険)なら、外気からの酸素の供給を断つためドアに目張り(ガムテープなどで)をし、排気口も塞ぐ。
・乾燥機のヒーターの電源を切る。内部のファンに関しては止めるか、止めないか意見が分かれるところです。 止めてしまうと乾燥機自体を痛めてしまう可能性もありますし、風を当てることで火を広げてしまう可能性もあります。また完全に電源を切ってしまうと内部の温度が判らなくなる弊害もあります。
・煙が少なくなって来て、温度も下がって来ても完全に冷めるまではドアを開けてはいけません。酸素が供給されて急に燃え上がる危険があります。
・状況が良くならないなら排気ダクトから
炭酸ガス消火器を噴射する。
(まだ使ったことはないけど、これが有効だと信じています) 酸素の遮断と温度を下げる効果が期待できる。
※ドアを開けての噴射は危険!
※炭酸ガスにより酸欠に注意!
・注水はパレットの下段まで水が至りにくいので効果は低い。さらに乾燥機の電気系統が生きている際には感電、短絡の危険もある。
|
【マッフル稼働時の停電対策】
・マッフルがまだ高温で稼働しているときに停電した場合についても考えておく必要があります。
・特に600℃以上の高温の場合、あるいは発煙中の場合そのままにしておくと危険かもしれません。
・600℃以下でかつ発煙していない場合にはドアを開けずにそのままにしておいてもおそらく大丈夫でしょう。
・高温の場合、かつ発煙が無い場合は、ドアを半開きにしてなるべく早く600℃以下に冷却する。ドアをあける際には特に気をつける。心配なら開けない。通常、高温時にはファンが作動して機器本体を冷却しているがそれが止まってしまうため、うちわで筺体をあおいで冷ます。かつ、冷えるまでは傍を離れない。
・高温かつ発煙中の場合、
ドアを開けてはいけない!
部屋の換気も同時に止まってしまい、排煙出来ないので最悪。煙を二時燃焼させられる状況なら燃やす。それも出来ない状況なら、うちわで筺体をあおぎながら温度が下がる、あるいは発煙が止まるまで待つ。極力、傍を離れない。
間違っても注水などしない!危険!
・停電復帰時に不用意な昇温が始まらないようにプラグを抜くか、ブレーカーを切っておく。
他の電気機器についてもそうしておいた方が良い。
いずれにしても事態を想定して対策しておきましょう。
・その他、オーブンや燃焼部が高温になる機器は同様の危険が想定されます。(CHN計の燃焼管など)
・実は乾燥機も停電すると発熱部へ急に風が送られなくなるため、一時的に加熱する場合があるので停電直後は要注意!
停電復帰後の動作は機器により違うので知っておいた方がいい。
そのまま止まっているものと、自動で復帰するものがある。自動で復帰すると危険な機器はブレーカーを落とすかプラグを抜いておく。
【破砕機の安全について】
はまた別途、書かせていただきます(準備中)
もう一度念のため。。。
以上はごみを分析する同志が事故に合わないよう参考に書いてみました。これが必ずしも正しいとは限りませんし、この通りにやって被害が増大しても責任も取れません。が、ほんの少しでも参考になれば幸いです。事態を想定して対策して置くことも大切です。そして何より、そうならないように予防する事が大切です。
それでは安全に、正しくごみ分析しましょう。
●安全について2
  

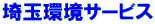 では では
環整95号によるごみ質分析全般。サンプリング、単位容積重量測定、乾燥・水分測定、組成分析、灰分測定のほか、詳細組成分析、発熱量の実測、元素分析なども可能です。 お気軽にご連絡ください。 |
|