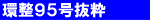

【一般廃棄物処理事業に対する
指導に伴う留意事項について】
公布日:昭和52年11月4日
環整95号
[改定]平成2年2月1日 衛環22号
(各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて
環境衛生局水道環境部環境整備課長通達)
一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について、昭和五二年一一月四日環整第九五号厚生省環境衛生局水道環境部長通知
からの抜粋(ごみ質の分析方法)
 全文は環境省HPをご覧下さい。 全文は環境省HPをご覧下さい。
ごみ質の分析方法
(環整95号別表から抜粋)
ごみ質の分析方法は、以下により行うことを標準とするが、他に適正と認められる方法をとっている市町村にあつては、従前のとおりとして差し支えない。
1 試料の採取
(1) 収集・運搬車からの採取
無作為に抽出した収集・運搬車から一台あたり10kg以上、合計200kg以上を採取する。
(2) ごみピットからの採取
ピット内のごみを十分混合したのち、200kg以上採取する。
2 試料の調製
採取した試料は、乾燥したコンクリート等の床上で、スコップ等でよく混合し、袋づめのごみは中味を取り出し、とくに大きなものは適当に細分する。つぎに、試料を十分に混合しつつ、四分法により数回縮分し、試料として5〜10kgを採取する。
注 縮分の途中で、目につく大きな廃棄物(とくに毛布、タイヤ、木竹、石油かん等破砕しにくいもの)については、あらかじめ別にとり出しておき、最後にそれを細断して試料に加えることが望ましい。例えば四回、四分法で縮分する場合、二回目終了後に毛布をとり出せば、その毛布は、さらに二回の縮分によつて1/22=1/4に減量されるはずであるから、毛布全重量の1/4を試料に加えることとなる。
3 測定分析
(1) 単位容積重量
2の試料を容量既知の容器に入れ30cm位の所から三回落とし目減りしたならば、目減り分だけ更に試料を加える。単位容積重量(または見かけ比重)は、次式(1)により算出する。
単位容積重量(kg/m3)=
試料重量〔kg〕/容器の容量〔m3〕…(1)
(2) 水分
3の(1)に用いた試料を秤量したのち、乾燥器等を用いて105℃±5℃で、恒量を得るまで乾燥し秤量する。水分は次式(2)により算出する。
水分(%)=((乾燥前の重量〔kg〕
−乾燥後の重量〔kg〕)
/乾燥前の重量〔kg〕)×100 …(2)
(3) ごみの種類組成分析
3の(2)に用いた試料の全量をビニールシート等に拡げて次の六組成を標準として組成ごとに秤量し、重量比(%)を求める。
1 紙・布類
2 ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類
3 木・竹・ワラ類
4 ちゆう芥類
(動植物性残渣、卵殻、貝殻を含む。)
5 不燃物類
6 その他
(孔眼寸法約5mmのふるいを
通過したもの)
(4) 灰分
3の(3)で分別した六組成のうち、不燃物類を除き、各組成ごとに破砕機を用いて2mm以下に粉砕し、その一部をルツボに入れて105℃±5℃で2時間加熱する。これを秤量したのち、電気炉を用いて800℃で2時間強熱し、秤量する。灰分は、次式(3)、(4)および(5)により算出する。
各組成の灰分(%)=(強熱後の重量〔kg〕
/強熱前の重量〔kg〕)×100 …(3)
乾燥ごみの灰分(%)=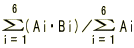
…(4)
Ai:(3)で求めた各組成iの重量比(%)
Bi:各組成iの灰分(%)
(不燃物類については100とする。)
生ごみの灰分(%)=乾燥ごみの灰分(%)
×((100−水分(%))/100) …(5)
(5) 可燃分
可燃分は次式(6)により算出する。
可燃分(%)=
100−水分(%)−生ごみの灰分 …(6)
(6) 低位発熱量
生ごみの低位発熱量は、次式(7)により推定することができる。
HI = 4,500 V − 600 W …(7)
HI:生ごみの低位発熱量(kcal/kg)
V:生ごみの可燃分(%)
W:生ごみの水分(%)
4 ごみ質分析を行うに際しての留意事項
(1) 試料の採取及び縮分はじん速に行うこと。
(2) 水分測定のための乾燥前重量の秤量を、試料採取時ではなく他日行う場合は、水分に変動が生じないよう密封保存すること。
(3) ピットわきで作業する場合には、転落等の事故が生じないよう作業監督者をつけ、安全をはかること。
(4) 縮分及びごみの分別等、直接生ごみに触れる作業を行う時は、けがをしないよう、また万一けがをした場合もすぐさま消毒等の応急措置がとれるようにしておくこと。
|
環整95号(平成2年2月1日改定 衛環22号)
(各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて環境衛生局水道環境部環境整備課長通達)では、
ごみ質 年四回以上、焼却残渣の熱しやく減量 月一回以上 測定する事となっています。

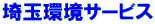 では では
環整95号によるサンプリング、単位容積重量測定、水分測定、組成分析、灰分測定のほか、詳細組成分析、発熱量の実測、元素分析なども可能です。 お気軽にご連絡ください。 |
|
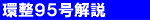

 環整95号はごみ質分析の根拠となる条文ですが基本的な部分のみしか記述されていません。 環整95号はごみ質分析の根拠となる条文ですが基本的な部分のみしか記述されていません。
(正式な名称はとても長い)
また、他の環境分析などと違いJIS化されていない部分も多々あります。
また、最低限の項目のみしか規定されていません
・組成項目が6区分しかない。
・発熱量測定が計算値のみしか規定がない。
・元素組成測定の規程がない。 など
実際には、さらに細かく、あるいは追加項目を実施する場合も多くあります。
 ここではごみ質分析についての項のみ抜粋していますが、全文については
環境省のホームページを参照下さい。 ここではごみ質分析についての項のみ抜粋していますが、全文については
環境省のホームページを参照下さい。
 ごみ分析の流れ ごみ分析の流れ
 基本はこれだが、他に適正と認められる方法でやっているなら、それでもよい、とのこと。 基本はこれだが、他に適正と認められる方法でやっているなら、それでもよい、とのこと。
 試料の採取及び、試料の調製に関しては、いかに代表的なサンプルを得るかが最大のポイントとなる。四分法を用いて縮分する。 試料の採取及び、試料の調製に関しては、いかに代表的なサンプルを得るかが最大のポイントとなる。四分法を用いて縮分する。
 円すい四分法 円すい四分法
 袋に入っているものは出し、よく混合し、偏りのないように気を配る。混合に適さないもの(大きなものなど)はあらかじめ別に取り出しておき後に縮分した比率で加える。 袋に入っているものは出し、よく混合し、偏りのないように気を配る。混合に適さないもの(大きなものなど)はあらかじめ別に取り出しておき後に縮分した比率で加える。
 元のごみを見て、代表する試料が採取できたか確認する事も必要。偏りがあるようなら必要に応じ再度、サンプリングする。(たまたま草木ばかりだったりすることもある) 元のごみを見て、代表する試料が採取できたか確認する事も必要。偏りがあるようなら必要に応じ再度、サンプリングする。(たまたま草木ばかりだったりすることもある)
 5〜10kg採取する。少なすぎると、試料のバラツキの影響が大きくなるし、多すぎると乾燥させる時間が長くなったり、分別に余分な工数が掛かる。 5〜10kg採取する。少なすぎると、試料のバラツキの影響が大きくなるし、多すぎると乾燥させる時間が長くなったり、分別に余分な工数が掛かる。
「ごみ焼却施設各種試験マニュアル」では10〜20kg以上となっているが通常は5〜10kg採取とすることも多い。
 参考図書の紹介 参考図書の紹介
  
 単位容積重量、見掛け比重の測定は原則、現場で行う。詰め込んだり、運搬すると容量が変わってしまう。(かさ密度、かさ比重などと呼ぶこともあるようです) 単位容積重量、見掛け比重の測定は原則、現場で行う。詰め込んだり、運搬すると容量が変わってしまう。(かさ密度、かさ比重などと呼ぶこともあるようです)
単位はkg/m3のほかkg/Lなどが一般的。
1000 kg/m3 = 1.000 kg/L
 容量既知の容器は40〜90L程度のポリバケツや、箱などを使う。 容量既知の容器は40〜90L程度のポリバケツや、箱などを使う。

 熱風循環式等の乾燥機で乾燥させる。高温による爆発、発火に特に注意する。変質、変形等にも注意する。 熱風循環式等の乾燥機で乾燥させる。高温による爆発、発火に特に注意する。変質、変形等にも注意する。
 安全について 安全について
 禁忌品(採取の際にも十分気をつける) 禁忌品(採取の際にも十分気をつける)
カセットコンロのボンベ、スプレー缶、ライター、マッチ、花火、有機溶剤(接着剤、ペンキ、マニキア、香水なども)などは乾燥機に入れない。
 物理組成分析(分別) 物理組成分析(分別)
 環整では組成項目は非常に大まかです。さらに細かく分別することも多いかと思われます。 環整では組成項目は非常に大まかです。さらに細かく分別することも多いかと思われます。
 組成項目(細分例) 組成項目(細分例)
 紙類と布類は別にすることもある。 紙類と布類は別にすることもある。
 ビニール・合成樹脂類とゴム類と皮革類を別にすることもある。 ビニール・合成樹脂類とゴム類と皮革類を別にすることもある。
 ちゆう芥類(厨芥類)。食品系(材料、カス、食べ残しなど)。 ちゆう芥類(厨芥類)。食品系(材料、カス、食べ残しなど)。
 不燃物類。金属類、ガラス類、石、セトモノ、などを含む。 不燃物類。金属類、ガラス類、石、セトモノ、などを含む。
 紙おむつ、不織布マスク、使い捨てカイロ、乾燥剤などはどれに分類するか意見が分かれる事もあるので事前に確認できればしたい。(重量的にも少なからず発生することが多い) 紙おむつ、不織布マスク、使い捨てカイロ、乾燥剤などはどれに分類するか意見が分かれる事もあるので事前に確認できればしたい。(重量的にも少なからず発生することが多い)
 ごみの3成分 (水分、灰分、可燃分) ごみの3成分 (水分、灰分、可燃分)
 灰分測定 灰分測定
 灰分測定は可燃物を実際に800℃で燃やしてどの位の割合の灰が残るかを調べるもの。不燃物は100%燃え残るものとして算入する。 灰分測定は可燃物を実際に800℃で燃やしてどの位の割合の灰が残るかを調べるもの。不燃物は100%燃え残るものとして算入する。
 生ごみ灰分とは乾燥前のごみの重量を分母としたときの値。 生ごみ灰分とは乾燥前のごみの重量を分母としたときの値。
  
 ごみの3成分 ごみの3成分
 可燃分は元のごみ重量(乾燥前)から水分と生ごみ灰分を引いたもの。水分以外の燃えて、なくなったものを可燃分としている。 可燃分は元のごみ重量(乾燥前)から水分と生ごみ灰分を引いたもの。水分以外の燃えて、なくなったものを可燃分としている。
 水分、生ごみ灰分(単に灰分と言うこともある)、可燃分を”ごみの3成分”と言い、ごみ質の大切な指標のひとつです。 水分、生ごみ灰分(単に灰分と言うこともある)、可燃分を”ごみの3成分”と言い、ごみ質の大切な指標のひとつです。
 (7)式は”3成分による推定式”と呼ばれている式で、生ごみの可燃分の発熱量を一律に4500cal/gに仮定しています。 (7)式は”3成分による推定式”と呼ばれている式で、生ごみの可燃分の発熱量を一律に4500cal/gに仮定しています。
HI = 45 V − 6 W
実際の発熱量は組成の内容で大きく変化しますので実測値と大きく異なる場合もあります。可燃分を求めるためには物理組成分析と灰分測定が必要になります。他にもいろいろな推定式が研究され考案されています。
 発熱量推定値 発熱量推定値 
 実際に調製した試料を燃やし、発熱量を実測して低位発熱量を求める場合もあります。 実際に調製した試料を燃やし、発熱量を実測して低位発熱量を求める場合もあります。
 発熱量(低位、高位発熱量) 発熱量(低位、高位発熱量)
 低位発熱量は生ごみを燃やした際の発熱量を知る上で大切な指標となります。 低位発熱量は生ごみを燃やした際の発熱量を知る上で大切な指標となります。
  
 怪我や事故のないように十分に留意する。 怪我や事故のないように十分に留意する。
・クレーンとの接触
・ピットへの転落
・怪我とそれに伴う感染 などなど
・環整95号は昭和52年以来、ごみ分析の基本条項であり、今日においても分析調査の拠り所です。しかし、内容的には昨今の現状との乖離も見られ、この環整95号を踏まえた上で上乗せした仕様で分析調査をすることがほとんでです。
・組成項目が6区分しかない。最近では10〜12区分、あるいはそれ以上に分類することもあります。
 物理組成分析 物理組成分析
 細分組成項目例 細分組成項目例
・発熱量測定が計算値のみしか規定がない。
実測値も併用しているところが多いようです。
 低位高位発熱量 低位高位発熱量
 発熱量推算値 発熱量推算値
・元素組成測定の規定がない。
基本は炭素C、水素H、窒素N。低位発熱量の実測値を求める場合は水素の測定が必要になります。さらに硫黄S、塩素Clなど。(減算法で酸素O)など(ごみの6元素) |