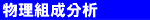

�@��95���ł́h�g����ޕ����h�ƌĂ�ł���B��ʂɂ́h���ݑg�����͒����h�A�h�g�����́h�A�h���ʁh�A�h�d�����h�Ȃǂƌ������Ƃ�����B
�@�ȉ��悤�ȍ��ڂɎd�������ďd�ʊ����ׂ�H���B���X�T���ł͊�����ԂłU���ڂɕ��ނ���ƂȂ��Ă���B���A����Ԃŕ�������A����ɍׂ������ڂɕ��ނ��邱�Ƃ�����B�s�R���݁A�e�傲�݁A���ƌn���݁A�j�ӂ��݂Ȃǂ͐�����A�g�����e���傫���قȂ邽�߁A�ʓr�A�g�����ڂ╪�͒������@����������K�v������B�܂��A�ړI���͂����肳���ĕ��ލ��ڂ�ݒ肷��K�v������B
���X�T���̍���
(3)�@���݂̎�ޑg������
�@3��(2)�ɗp���������̑S�ʂ��r�j�[���V�[�g���Ɋg���Ď��̘Z�g����W���Ƃ��đg�����Ƃɔ��ʂ��A�d�ʔ�(��)�����߂�B
�@�@�@���E�z��
�@�A�@�r�j�[���E���������E�S���E��v��
�@�B�@�E�|�E������
�@�C�@���䂤�H��
�@�@(���A�����c�ԁA���k�A�L�k���܂ށB)
�@�D�@�s�R����
�@�E�@���̑�
�@�@(�E�ᐡ�@���mm�̂ӂ邢��ʉ߂�������)
�@ �g�����ځi�ו���j �g�����ځi�ו���j
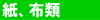
 �h���h�Ɓh�z�h�Ƃɕ����邱�Ƃ�����B �h���h�Ɓh�z�h�Ƃɕ����邱�Ƃ�����B
 ��T�Ɏ��Ƃ����Ă��A�r�j�[����������R�[�e�B���O����Ă�����̂�A�C���N���i���h�z����Ă�����̂Ȃǂ�����B�h�ċp�s�K���h�A�h�ė��p�ɕs�����Ȏ��h�Ƃ��ĕʂɕ����邱�Ƃ�����B ��T�Ɏ��Ƃ����Ă��A�r�j�[����������R�[�e�B���O����Ă�����̂�A�C���N���i���h�z����Ă�����̂Ȃǂ�����B�h�ċp�s�K���h�A�h�ė��p�ɕs�����Ȏ��h�Ƃ��ĕʂɕ����邱�Ƃ�����B
�E�������A�Đ��ł��邩�ǂ����͍Đ��Z�p�̐i����Đ��Ǝ҂̑Ή��͂ɂ���Ă��ς���Ă���B
 �z�ƌ����`��������Ă��Ă��A���낢��ȑf�ނ�����i�K���X�@�ہA�����@�ہA�ΖȂȂǕs�R���̂��̂�����j�B�т�ȏ�̂��̂��܂߂đ@�ۗނƂ��邱�Ƃ�����B�ؖȂƉ��@�ł͑傫������i���M�ʁA���f�g���Ȃǁj���قȂ�B �z�ƌ����`��������Ă��Ă��A���낢��ȑf�ނ�����i�K���X�@�ہA�����@�ہA�ΖȂȂǕs�R���̂��̂�����j�B�т�ȏ�̂��̂��܂߂đ@�ۗނƂ��邱�Ƃ�����B�ؖȂƉ��@�ł͑傫������i���M�ʁA���f�g���Ȃǁj���قȂ�B
�z�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ă��@�ۏ�̂��̂��܂߂邱�Ƃ������B�h�@�ۗ��h�Ƃ��邱�Ƃ�����B
�@ �g�����ځi�ו���j �g�����ځi�ו���j
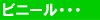
 �h�r�j�[���E���������E�S���E��v���h �h�r�j�[���E���������E�S���E��v���h
�܂Ƃ߂āh�����q�n�h�ƕ\�����邱�Ƃ�����B
�v���X�`�b�N�ނ��܂ށB�h�v���X�`�b�N�ށh�Ɓh�S���E��v�h���邱�Ƃ�����B��v���h�q�J�N�h�ƓǂށB�h�q�J���h�ł͂���܂���B
 �v���X�`�b�N�̍ގ��ׂ��肷�邱�Ƃ�����B �v���X�`�b�N�̍ގ��ׂ��肷�邱�Ƃ�����B
�@PE(�|���G�`����),�@PP(�|���v���s����),
�@PS(�|���X�`����),�@PET(�y�b�g),
�@PVC(�����r�j�[��)�Ȃǂ���Ȃ��̂ł��B
 �h���������h���Ă�����ƌÂ��������ł����ˁB �h���������h���Ă�����ƌÂ��������ł����ˁB
�@ �g�����ځi�ו���j �g�����ځi�ו���j
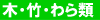
 ��ʂ̉R���݂ɓ����Ă���E�|�E���ނɂ͊��蔢�A�ܗk�}�A�Ă����̋��A�A�C�X�N���[���̖_�Ȃǂ�����B����}�◎���t�Ȃǂ���ʂɓ����Ă��邱�Ƃ�����B�ԕr�̉Ԃ�A�ؐ��i�Ȃǂ�����B ��ʂ̉R���݂ɓ����Ă���E�|�E���ނɂ͊��蔢�A�ܗk�}�A�Ă����̋��A�A�C�X�N���[���̖_�Ȃǂ�����B����}�◎���t�Ȃǂ���ʂɓ����Ă��邱�Ƃ�����B�ԕr�̉Ԃ�A�ؐ��i�Ȃǂ�����B
 ���ؗށA�ؑ��ށA�ؒ|�ނȂǂƂ��邱�Ƃ�����B ���ؗށA�ؑ��ށA�ؒ|�ނȂǂƂ��邱�Ƃ�����B
 �ؐ��Ɍ����Ă��v���X�`�b�N���⎆���ƌ�����������̂ŗv���ӁB �ؐ��Ɍ����Ă��v���X�`�b�N���⎆���ƌ�����������̂ŗv���ӁB
 ���܂ǂ��̓������������邱�Ƃ͂��܂肠��܂���B�h�m�h�Ƃ����������Ȃ��Ȃ��g���@�������@�������܂���B�������̌�Ȃǂɏ��蕨�Ɏg�p�������̂��܂Ƃ܂��ďo�邱�Ƃ�����܂��B ���܂ǂ��̓������������邱�Ƃ͂��܂肠��܂���B�h�m�h�Ƃ����������Ȃ��Ȃ��g���@�������@�������܂���B�������̌�Ȃǂɏ��蕨�Ɏg�p�������̂��܂Ƃ܂��ďo�邱�Ƃ�����܂��B
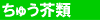 �@�i�~�H�ށj �@�i�~�H�ށj
 �����J�X��H�c���ȂǁB �����J�X��H�c���ȂǁB
 �ʕ��̔���A�R�[�q�[�̃J�X�ȂNJ܂ށB �ʕ��̔���A�R�[�q�[�̃J�X�ȂNJ܂ށB
 ���◑�̊k�����܂ށB ���◑�̊k�����܂ށB
��ʂɐ����̊������������Ƃ������B
�@���◑�ƁA���ʕ��Ȃǂł͐������Ⴄ���A���M�ʁA�D���Ȃǂ����R�A�S���Ⴂ�܂��B�ǂ̂悤�ȓ��e���A�ώ@���Ă������Ƃ��d�v�ł��B�A�����̂��̂Ɠ������̂��̂��邱�Ƃ�����܂��B
��ʂ̖��J���̐H�i�Ȃǂ�����Ɣ߂����v�������܂��B
 �H�i���T�C�N���A�H�i���X�A�t�[�h���X�ɒ��ڂ��������ł͂���ɍׂ������ނ����邱�Ƃ�����܂��B�i�ܖ������A�J���̗L���i�����p�H�i�j�A���������Ȃ̂��H�c���Ȃ̂��A�ߏ菜���A�s�H���Ȃǁj �H�i���T�C�N���A�H�i���X�A�t�[�h���X�ɒ��ڂ��������ł͂���ɍׂ������ނ����邱�Ƃ�����܂��B�i�ܖ������A�J���̗L���i�����p�H�i�j�A���������Ȃ̂��H�c���Ȃ̂��A�ߏ菜���A�s�H���Ȃǁj
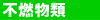
 �K���X�ށA�����ށA�Z�g���m�E�E���Ȃǂ��܂ށB �K���X�ށA�����ށA�Z�g���m�E�E���Ȃǂ��܂ށB
 �G�߂ɂ���Ďg���̂ăJ�C�������������Ƃ�����B �G�߂ɂ���Ďg���̂ăJ�C�������������Ƃ�����B
�@ �g�����ځi�ו���j �g�����ځi�ו���j
 �V���J�Q���A�ΊD�Ȃǂ̊����܂��s�R���Ƃ��邱�Ƃ������B �V���J�Q���A�ΊD�Ȃǂ̊����܂��s�R���Ƃ��邱�Ƃ������B
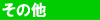
 ��ʂɂ͂ӂ邢��ʉ߂����G���A��G���i���傤�����̂��Ɓj�B�ӂ邢�̖ڂ͂T�����Ƃ��邱�Ƃ����� ��ʂɂ͂ӂ邢��ʉ߂����G���A��G���i���傤�����̂��Ɓj�B�ӂ邢�̖ڂ͂T�����Ƃ��邱�Ƃ�����
 ���̍��ڂɊ܂߂��Ȃ����̂����̑��ɓ���܂��B�Ⴆ�E�E�E ���̍��ڂɊ܂߂��Ȃ����̂����̑��ɓ���܂��B�Ⴆ�E�E�E
�@��������A�N�������A���[�\�N�A���A�Ό��A�˂��݂̎��[�A�Ȃ�����Ȃ����́@�ȂǁE�E�E
 �h���̑��h�̊����������Ƒg�����͒����̈Ӗ��������̂ň�ʂɂ͏��Ȃ��ق����悢�B�����I�Ȃ��̂�����Ƃ��͓��e���L�^���Ă������Ƃ��]�܂����B �h���̑��h�̊����������Ƒg�����͒����̈Ӗ��������̂ň�ʂɂ͏��Ȃ��ق����悢�B�����I�Ȃ��̂�����Ƃ��͓��e���L�^���Ă������Ƃ��]�܂����B
 �����h���̑��h�ɂ���̂��͎d�l�ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ�����܂��B �����h���̑��h�ɂ���̂��͎d�l�ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ�����܂��B
����ʓI�ɂ́h���̑��̉R���h�Ƃ̉��߂���A�s�R���ƍl��������̂͊܂߂Ȃ����Ƃ������悤�ł��B�i���̑��ɓ��ꂽ���̂͒ʏ�͔j�ӂ���Ȃǂ��ĈȌ�̕��͂̑ΏۂɂȂ�܂��j
 �g�����ڕ\����낤�Ƃ��Ă���̂ł�����A����A�h���̑��̉R���h�A�h���̑��̕s�R���h�̗�������Ă����Ə�����܂��B�z��O�̂��̂┻�f�ɍ�����̂��o�Ă��܂�����B �g�����ڕ\����낤�Ƃ��Ă���̂ł�����A����A�h���̑��̉R���h�A�h���̑��̕s�R���h�̗�������Ă����Ə�����܂��B�z��O�̂��̂┻�f�ɍ�����̂��o�Ă��܂�����B
|

�@����ƂƂ��ɐV�f�ނ�V���������f�ނ��o�ꂵ�A�܂����H�Z�p���i������ޑg�����ޒ����A���ʎ��W�A���T�C�N�������G�ɂȂ荂�x�ȋZ�p���K�v�ɂȂ�܂��B
�h���݁h�ɂ͂���Ȃ��̂������Ă��܂�
�@�i�����f�ނ�V�f�ނȂǁj
�y�����ނz
 �����ŋ߂͈�ʂ��݂ɕK���ƌ����Ă������炢�A�����ނ������Ă��܂��B�h���h���ނ��ƌ����Ă��A�قƂ�ǁA���邢�͑S�������g���Ă��Ȃ��ƌ����b�������܂��i�����q���s�D�z�A���z���������q�Ȃǁj�B�����ł��Ȃ����炢�̏d�ʂł��邱�Ƃ��������A��ʂ̐����i���d�̐��\�{���琔�S�{�̐����z���A�ێ��ł���炵���j���܂�ł��邱�Ƃ������B���܂��ɓ��e���������ɍ��邱�Ƃ������B
�����ŋ߂͈�ʂ��݂ɕK���ƌ����Ă������炢�A�����ނ������Ă��܂��B�h���h���ނ��ƌ����Ă��A�قƂ�ǁA���邢�͑S�������g���Ă��Ȃ��ƌ����b�������܂��i�����q���s�D�z�A���z���������q�Ȃǁj�B�����ł��Ȃ����炢�̏d�ʂł��邱�Ƃ��������A��ʂ̐����i���d�̐��\�{���琔�S�{�̐����z���A�ێ��ł���炵���j���܂�ł��邱�Ƃ������B���܂��ɓ��e���������ɍ��邱�Ƃ������B
�y�ǎ��z
 �ǎ��Ȃǂ����Ǝv������A�����q�n�̃t�B���������荇�킹�Ă�������A�S�Ă������q�n�ŁA����S���g�p���Ă��Ȃ�������B �ǎ��Ȃǂ����Ǝv������A�����q�n�̃t�B���������荇�킹�Ă�������A�S�Ă������q�n�ŁA����S���g�p���Ă��Ȃ�������B
�y�s�D�z�z
 �@�ۂ�D�炸�ɗ��ݍ��킹���V�[�g��̂��̂������炵�����A�a���Ƌ�ʂ��ɂ������̂�����B�f�ނ������q�n�̂��̂�A�K���X�@�ۂ̂��̂Ȃǂ�����B�r�j�[���ƒ��荇�킹�Ă������������B�g���̂Ẵ}�X�N�A�e��t�B���^�[�ȂNJe��p�r�ɑ��p����Ă���B�����A���̎g���̂ĕs�D�z�}�X�N�������������Ă���B�������ǂ��Ɏd�������邩���߂Ă����K�v������B
�@�ۂ�D�炸�ɗ��ݍ��킹���V�[�g��̂��̂������炵�����A�a���Ƌ�ʂ��ɂ������̂�����B�f�ނ������q�n�̂��̂�A�K���X�@�ۂ̂��̂Ȃǂ�����B�r�j�[���ƒ��荇�킹�Ă������������B�g���̂Ẵ}�X�N�A�e��t�B���^�[�ȂNJe��p�r�ɑ��p����Ă���B�����A���̎g���̂ĕs�D�z�}�X�N�������������Ă���B�������ǂ��Ɏd�������邩���߂Ă����K�v������B
�y�l�R���z
 �l�R�Ȃǂ̃y�b�g�̃g�C���Ɏg�����́B���Ƃ����Ă��s�̂̂��̂͂�����h���h�łȂ����̂������i���A�A�z���A�V���J�Q���A������A�Ȃǂ������Ƃ������́j�B�R���Ƃ��ĔR�₹�邱�Ƃ�搂��Ă��鏤�i������悤�����A�����̂ɂ���đΉ����Ⴄ�ꍇ������B
�l�R�Ȃǂ̃y�b�g�̃g�C���Ɏg�����́B���Ƃ����Ă��s�̂̂��̂͂�����h���h�łȂ����̂������i���A�A�z���A�V���J�Q���A������A�Ȃǂ������Ƃ������́j�B�R���Ƃ��ĔR�₹�邱�Ƃ�搂��Ă��鏤�i������悤�����A�����̂ɂ���đΉ����Ⴄ�ꍇ������B
�y�r�j�[���z
 ��ʂɃr�j�[���ƌ����ƃ|���G�`�������̃r�j�[���܂�z���������������ł��傤���H ���݂�����ۂɏo�Ă�����̂ɂ́A�������̐��������w�ɒ��荇�킹�Ă�������A�\�ʂ����H��R�[�e�B���O���Ă�������A�ޗ����̂��̂ɂ��낢��Ȃ��̂��Y�����Ă�������ƒP���ł͂���܂���B���ɐH�i�̃p�b�N�Ȃǂ͍��x�ȕi���Ǘ�����S����ۂׁA���낢��ȍH�v������Ă�����̂������悤�ł��B
���̔������b�v���T�w�������肷�邻���ł��B
��ʂɃr�j�[���ƌ����ƃ|���G�`�������̃r�j�[���܂�z���������������ł��傤���H ���݂�����ۂɏo�Ă�����̂ɂ́A�������̐��������w�ɒ��荇�킹�Ă�������A�\�ʂ����H��R�[�e�B���O���Ă�������A�ޗ����̂��̂ɂ��낢��Ȃ��̂��Y�����Ă�������ƒP���ł͂���܂���B���ɐH�i�̃p�b�N�Ȃǂ͍��x�ȕi���Ǘ�����S����ۂׁA���낢��ȍH�v������Ă�����̂������悤�ł��B
���̔������b�v���T�w�������肷�邻���ł��B
 ��F�œ����悤�Ɍ����Ă��A���~�ƒ��荇�킹�Ă�������A�������Ă�������A�P�ɒ��F���Ă�������ƂȂ��Ȃ��ȒP�ł͂���܂���B ��F�œ����悤�Ɍ����Ă��A���~�ƒ��荇�킹�Ă�������A�������Ă�������A�P�ɒ��F���Ă�������ƂȂ��Ȃ��ȒP�ł͂���܂���B
 �������u�R���v�Ƃ�����A�u�s�R���v�Ƃ�����A�u���₹�Ȃ����݁v�A�u�R�₳�Ȃ����݁v�Ƃ�����Ƃ��낢��ł��B �w��S�~�܂ɖ�܂�Y�����A���M�ʂ������R���Ƃ���������܂��B
�������u�R���v�Ƃ�����A�u�s�R���v�Ƃ�����A�u���₹�Ȃ����݁v�A�u�R�₳�Ȃ����݁v�Ƃ�����Ƃ��낢��ł��B �w��S�~�܂ɖ�܂�Y�����A���M�ʂ������R���Ƃ���������܂��B
�y�S���E��v�z
 �S���ƌ����Ă��S���łȂ������肵�܂��B �S���ƌ����Ă��S���łȂ������肵�܂��B
�S���z�[�X�A�S�����C�A�S���{�[�g���S���łȂ������肵�܂���ˁB�V���R���S�����ăS���ł����H
 ��v�ƌ����Ă���łȂ�������B������v���ĂȂ�ł��傤�H�����ڂɂ����f���Â炢�B ��v�ƌ����Ă���łȂ�������B������v���ĂȂ�ł��傤�H�����ڂɂ����f���Â炢�B
�y�g���̂ăJ�C���z
 �z�J�����A�z�b�J�C���Ȃǂ̏��i���Œm����g���̂ăJ�C���������G�߂ɂ͑�ʂɏo�Ă��邱�Ƃ�����܂��B
�z�J�����A�z�b�J�C���Ȃǂ̏��i���Œm����g���̂ăJ�C���������G�߂ɂ͑�ʂɏo�Ă��邱�Ƃ�����܂��B
�s�D�z�̑܂̒��ɍ��Y�A�S���Ȃǂ������Ă��܂��B��ʂɂ͂��̂܂܁h���̑��̕s�R���h�Ƃ��Ĉ������Ƃ������B
�y�����܂Ȃǁz
 �����܂ƌĂ�Ă�����̂ɂ����g�̓V���J�Q����ΊD�Ȃǂ�����܂��B �����悤�Ȍ`��̂��̂ɒE�_�f�܂Ȃǂ�����܂��B�悭����Ɠ��e���������Ă��邱�Ƃ������B��ʂɂ͂��̂܂܂��̑��̕s�R���Ƃ��Ĉ������Ƃ������B
�����܂ƌĂ�Ă�����̂ɂ����g�̓V���J�Q����ΊD�Ȃǂ�����܂��B �����悤�Ȍ`��̂��̂ɒE�_�f�܂Ȃǂ�����܂��B�悭����Ɠ��e���������Ă��邱�Ƃ������B��ʂɂ͂��̂܂܂��̑��̕s�R���Ƃ��Ĉ������Ƃ������B
�y�ۗ�܁A�~�M�܁z
 �ۗ�܂�~�M�ނ��ŋ߂͒������Ȃ��o�Ă��܂��B�ގ��I�ɂ͍����q�n�̗l�ł����A���̂������������܂�ł��܂��B��ʂɖ����ł��Ȃ��d�ʂ����邱�Ƃ����������Ă��܂��܂��B �ۗ�܂�~�M�ނ��ŋ߂͒������Ȃ��o�Ă��܂��B�ގ��I�ɂ͍����q�n�̗l�ł����A���̂������������܂�ł��܂��B��ʂɖ����ł��Ȃ��d�ʂ����邱�Ƃ����������Ă��܂��܂��B
�d�l�ɂ��v���X�`�b�N�ɂ�����A���̑��ɂ�����ƂȂ�܂����A�R�����g���c���Ă����̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�y�����A�����܂����v���X�`�b�N�z
 �ꌩ����ƕ��ʂ̃v���X�`�b�N�����A�������������邱�Ƃɂ���Ĉ�ʂ̔R�₹�邲�݂ɏo���邱�Ƃ�搂������i������B�ł��A�R�₷�ꍇ�A�����̓v���X�`�b�N��R�₷���ƂɂȂ邵�A�t�Ƀv���Ƃ��Ĕr�o���ꂽ�ꍇ�A�v���X�`�b�N�̃��T�C�N���̏�Q�ɂȂ�Ȃ����S�z�ł��B �ꌩ����ƕ��ʂ̃v���X�`�b�N�����A�������������邱�Ƃɂ���Ĉ�ʂ̔R�₹�邲�݂ɏo���邱�Ƃ�搂������i������B�ł��A�R�₷�ꍇ�A�����̓v���X�`�b�N��R�₷���ƂɂȂ邵�A�t�Ƀv���Ƃ��Ĕr�o���ꂽ�ꍇ�A�v���X�`�b�N�̃��T�C�N���̏�Q�ɂȂ�Ȃ����S�z�ł��B
�y�H�ׂ邱�Ƃ̂ł���H��A�X�g���[�z
�g���̂Ẵv���X�`�b�N�̎g�p�����炻���Ƃ������ƂŌ��ꂽ�H�ׂ邱�Ƃ̂ł���H���X�g���[�ȂǁB
�H�ׂ邱�Ƃ͂ł��邪�H�ו��Ƃ͌����ɂ����B�Ȃ̂Ő~�H�ɂ͂��ɂ����B����ɂ͎����i�Ƃ���ʂ��ɂ������̂�����B�R�����̑��H�H�Ƃ���Ƃ��̑����ǂ�ǂ������B
�@ �g�����ځi�ו���j �g�����ځi�ו���j
�@ ���X�T�������y�сA��� ���X�T�������y�сA���
�@ ���ݎ����̗͂��� ���ݎ����̗͂���
�@ �Q�l�}���̏Љ� �Q�l�}���̏Љ�
�@�@���ݕ��͂̎Q�l�ɂȂ�}���̏Љ�B
�@  

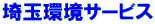 �ł� �ł�
���ݎ����͑S�ʂ��\�ł��B�g�����͂ł͑����ځA�v���g���A�e���d�������ɑΉ����܂��B�@�@���C�y�ɂ��A�����������B |
|